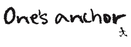ハンセン病の政策は「救民」という思想からでてきました。
「隔離」という施策も「救民」からでてきたといえます。
「外来治療でも、療養所からの退所でも世間の差別意識がある以上患者は苦しむので、患者にとって療養所が一番平安な場所」であると「救癩の父」といわれた光田健輔は、考えていたとのことです。
わたしは、この考え方に、既視感を覚えます。
1963年婦人公論に掲載された「誌上裁判 奇形児は殺されるべきか」において、水上勉が「奇形の子どもを太陽に向ける施設があればいいが、そんなものはない。そうした今の日本では、どうしても生かしておいたら辛いんだな。親も辛い、子も辛かろう」といい、その発言をついで戸川エマが「さっき水上さんがおっしゃったような花園に行ける施設が国家の予算で出来たら、と、そういうことを非常に強く感じます」とこたえます。
これらの発言は、のちのコロニーといわれる大規模施設建設の民衆的な心情をいいあらわしているように思えます。
そして、その論理の骨格は、世間の差別から隔離、保護することこそが、本人、家族のしあわせであるということです。
ハンセン病の場合、近代以降、封建的な身分差別と医学の発達による病原菌の発見がおりかさなるようにして差別を増幅しました。
国費で療養所を建設することから実際よりも声高に感染の恐れを喧伝し、隔離することで、その恐ろしさが実感され、病人を受け入れられない素地を地域、民衆レベルで作ってしまいました。
隔離が差別から守るのか、隔離によって差別が助長されたのかといえば、このことで差別は決定づけられたのです。
1946年、日本でも治療薬のプロミンが合成が成功し、不治の病であったハンセン病がなおる病気になりました。
隔離の根拠がなくなったのです。
日本近辺の国では、1960年にフィリピン、シンガポール、香港、台湾、韓国などが通院治療に切り替えました。占領下の沖縄でも同じです。
しかし、日本では隔離政策は見直されることはありませんでした。
日本でも「らい予防法」を改廃する動きは全患協(全国国立ハンゼン氏病療養所患者協議会)を中心にありました。
厚生省の課長クラスの人も廃止の意見を持っていました。
しかし、「法改正のためには一般世論、社会の認識を改める必要があり、簡単にはいかないだろう」という意見が厚生省内の大半だといわれています。療養所が強固に制度化されていたため、医療、生活、福祉が所内で充足して、完全隔離が完全に根を張り、法的根拠がないにもかかわらず、それの解き放ち方がわからなかったのです。
そのため、完全隔離というかたちはのこしたまま、入所者の処遇改善に予算を割くことになりました。
そして、時期を逸した「らい予防法」改廃は国際的な避難をあびてなお、存続しました。
そこには「世間の差別から保護するために」という奇妙な心情がはたらいていたように思えてなりません。